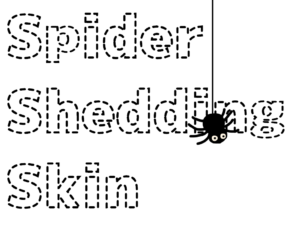目次
神社仏閣の聖域内には、参拝に訪れる人間以外にも、小さな生き物がたくさん暮らしています。
我々人間は、成人すると最長で2mを超えるものもある、大型生物です。
二足歩行で、左右手足の各五本の指を器用に使います。
知能も高く、巨大な建造物を作り、効率的に食べ物を生産・分配し、集団を形成しながら協力して生活を送ります。
私たち人間は体が大きく、無意識のうちに周囲の命を傷つけてしまうこともあります。
例えば境内では、こんなことが起こりがちです。
- 蚊やアブ、ハエにまとわりつかれて思わず叩いてしまう
- 足元の小さな虫を踏んでしまう
こうした出来事が「聖域」で起きたとき、普段以上に強い罪悪感を覚える方も多いのではないでしょうか。
先日、私自身もそんな体験をしました。
以下ちょっと憂鬱なお話注意。
|
|
|
|
|
|
↓
体験談:神社で小さな命を踏んでしまった
小さな神社に参拝したとき、拝殿前で足元がジャリジャリと音を立てていました。
最初は「貝殻かな?」と思っていたのですが、よく見ると小さなカタツムリの仲間――「キセルガイ」でした。
気づいたときにはすでに数匹を踏みつぶしてしまっていたのです。
無生物を壊すのと違い、命あるものを奪ってしまったと気づいた瞬間、強い罪悪感を覚えました。
しかも場所は神社、祈りの最中。
普段なら蚊を払う程度のことでも、境内での殺生には特別な「重さ」を感じました。
これは少し、示唆的だなと思ったので、書き留めておこうと思います。
『罪悪感』を心理学の視点で見る

<意味>自分の言動が他の人を傷つけ、罪の意識を感じてしまうこと
自分の失敗やミス、言動のために、周囲や他の人に迷惑をかけたとき、人は罪悪感を抱く。
致命的な失敗、宗教上のあやまち、不道徳な行いなどに対して罪悪感をもつのではなく、さして大きな失敗やミスでもないのに強い罪悪感を抱く人がいる。
往々にして自己卑下が強く、職場やプライベートでも、すぐに「すみません」と口にするタイプ。
適度な謙遜は人間関係の潤滑油といえるが、自己卑下が強くなりすぎると人生を楽しめなくなり、場合によってはうつ症状などが発症する。
引用元は「性格・感情辞典」なのでそちらにフォーカスしているのですが…
①致命的な失敗
②宗教上のあやまち
③不道徳な行い
この3つのうち、境内・聖域内での殺生は、②と③にあてはまりますね…。
心理学では、罪悪感は「自分の行動が他者を傷つけた」と感じたときに生じる感情とされます。
大きな過ちでなくても、真面目な人ほど強く抱きやすい感情です。
過剰になれば自己卑下につながり、心の負担になることもあります。
仏教における殺生と不殺生戒

「殺生」とは仏教用語で、「不殺生戒(ふせっしょうかい)」のことです。
すなわち 「命あるものを殺してはいけない」 という戒律です。
もっとも、この世には厳然と食物連鎖があり、命が命を支える仕組みが存在しています。
それは自然の摂理であり、避けることはできません。
仏教の「精進料理」では肉や魚、卵を用いませんが、野菜や穀物にも命があります。
生きている限り、私たちは他の命を「いただく」ことで生をつないでいるのです。
それは必要な行いであって、必ずしも「悪」と断じられるものではありません。
大切なのは、命を尊び、活かす姿勢です。
食事の際には感謝の心を持ち、不必要な殺生は避ける…その心構えが求められるのだと思います。
快楽を目的とする殺生や動物虐待はもちろん許されるものではありません。
しかし一方で、現実の営みの中で起こる殺生を、単純に白黒で裁くことはできないのではないでしょうか。
神道と仏教で異なる、殺生の捉え方
宗教上のタブーについて神社と仏閣で少し違うので、以下メモしておきます。
神社は「死」の穢れを厭う

神社では「穢れ」を忌み嫌う考え方が根づいています。
日本神話の黄泉の国の記述に由来するとされ、神様は「喪」を嫌う存在とされています。
そのため、喪中の参拝は大変失礼にあたります。
また「死」を連想させる毛皮やレザーの着用もマナー違反とされ、怪我などで血が出ている状態も避けるべきとされています。
神々の性質は「死」という概念と相容れないものである、と理解することができるでしょう。
ただし、これはあくまで人間の「死」に関わることです。
自然に囲まれた神社では、虫や動物の死骸が目に入ることもあります。
それらは「喪」とは異なり、必ずしも歓迎されるものではないものの、自然の摂理として受け入れられていると考えられます。
もちろん、小さな命であっても、境内での殺生が褒められることはありません。
ただし重要なのは、そうした行為の後に人間がどのような「心」や「思考」を持つか。
神様はその姿勢を見ておられるのではないでしょうか。
仏教では命を尊ぶ戒律がある

お寺の場合、仏教では人間であっても小さな命であっても、いずれも「殺生」として扱われます。
前述のとおり、私たちは生きている限り、他の命を糧として生命を維持しており、それは避けられない営みです。
しかし同時に、仏教においてはそれが戒められるべき行為でもあります。
聖域であれ俗世間であれ、仏教徒にとって殺生は御仏の教えに背く行為であり、罪であることに変わりはありません。
もっとも、仏は慈悲深い存在です。
殺人を犯した者であっても、仏教に帰依し出家することで救いを求めることができます。
反省の心を持つ者に対しては、救いの道が示されるのです。
したがって、お寺での殺生は「戒律破り」を仏の眼前でしてしまったことになります。
ただし、その場で反省し、救いを求めることができるのは、むしろ幸いであるとも言えるでしょう。
聖域で生き物を殺してしまったときの考え方

-
事実を受け止める
「わざとじゃないから関係ない」と切り捨てず、「良くないことをしてしまった」と認識する。 -
心の中で謝る
小さな命であっても、「ごめんなさい」と一言でも祈ることで気持ちが整います。 -
過剰に自分を責めすぎない
心理学的には、罪悪感を抱きすぎると自分を苦しめるだけ。中庸を意識することが大切です。 -
今後に生かす
次の参拝では足元に注意を払う、虫よけを準備するなど、学びを行動に変える。
神罰、仏罰が心配な方へ
私自身も過去に境内で蚊を払って殺してしまったことがありますが、それで神罰が下ったことはありません。
神社仏閣は「人が完璧であること」を求めているのではなく、「反省して次に活かす姿勢」を大切にしていると考えます。
もし不安なら、御前で「小さな命を奪ってしまい申し訳ありません」とお詫びの言葉を捧げるとよいでしょう。
特に夏場の参拝では、虫除けを持っていれば安心です。
虫よけで未然に防ぐのがおすすめ
境内で蚊を叩いてしまうと「バチが当たるのでは…」と心配になりますが、事前に虫よけを使えばその不安もなくなります。
参拝のたびに安心して過ごすためにも、携帯しておくのがおすすめです。
なお、神社仏閣で使うなら「殺虫」ではなく「忌避効果(寄せ付けない)」タイプが安心です◎
詳しい選び方は以下の記事でも解説しています。
【神社仏閣】夏の参拝に虫除けは必須!!必ず携帯して肌を守ろう!選び方や使うタイミングについて
おすすめの虫よけ
- 海外製・超強力タイプ:長時間効果が欲しい方におすすめ
- 日本製・安心タイプ:肌への優しさや香り重視ならサラテクトシリーズ
※いずれも忌避効果であり、虫を殺すものではありません。
まとめ|安心して参拝できるように

境内で生き物を殺してしまうと、強い罪悪感を覚えるかもしれません。
-
心理学的には、それは真面目さから来る自然な感情
-
神社仏閣の宗教観からは、不敬や戒律違反にあたるが「反省と今後の行動」が何より大切
つまり、必要以上に自分を責めることなく、真摯に謝り、次の参拝に活かしていけば良いのです。
- Q「境内で蚊を殺してしまったら罰が当たる?」
- A「大丈夫。神罰が下ることはなく、反省と今後の心がけが大切」
キセルガイ、ごめんね。
これからはもっと足元に気をつけようと思います。