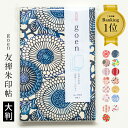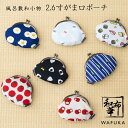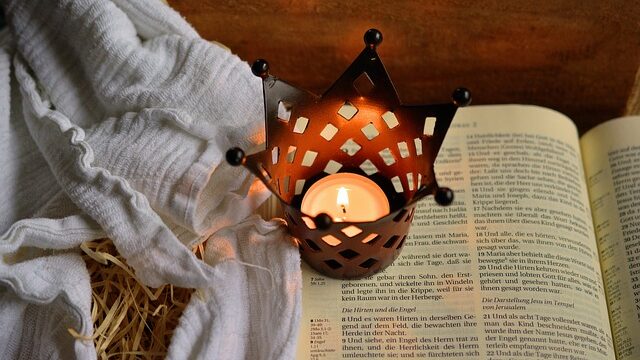目次
神社へ参拝するときに「何を持っていけばいいの?」と迷う方は多いと思います。
必ず持って行きたいのは、小銭・ハンカチ・御朱印帳・お守りやおみくじ(返納用)の4つ。
さらに御朱印巡りをする人や夏場に参拝する人には、虫除けスプレーやウェットティッシュといった便利アイテムも役立ちます。
この記事では、神社参拝の基本の持ち物から、シーン別の便利グッズまでをチェックリスト形式で解説します。
参拝前の準備にぜひお役立てください。
神社参拝の必須持ち物リスト(4つ)

神社参拝で最低限そろえておきたい基本アイテムは以下の4つです。
どれも忘れると意外に困るものばかりなので、事前に準備しておきましょう。
小銭(お賽銭・おみくじ用)
お賽銭やおみくじには小銭が必要です。普段キャッシュレス決済に慣れていると、神社で小銭不足に陥りがち。
100円玉を中心に数枚持っていくと安心です。
お賽銭の相場:5円~500円(気持ち次第でOK)
おみくじ:100~300円
お守り:800~1500円
お札:1000~3000円
最近は電子マネー対応の神社もありますが、全国的にはまだ少数派。現金を用意するのが無難です。
💡ワンポイント
硬貨の両替には手数料がかかる時代。1円・5円を大量に出すのは神社側にとって負担になる場合も。
扱いやすく明るい印象のある100円玉がおすすめです。
関連記事:お賽銭の詳しい記事はこちら
ハンカチ・ミニタオル(手水舎用)
参拝前に手を清める「手水」で必ず必要になるのがハンカチ。忘れると自然乾燥や服で拭くことになり、少し不便です。
- 手水舎での手や口拭きに使用
- 霊水や水みくじに触れるときも活躍
- 小さな神社では水が使えない場合もあるので、ウェットティッシュを代用しても◎
御朱印帳(御朱印巡りの証)
御朱印を集めている方にとっては必需品。旅行や遠方参拝の際に忘れると、せっかくの機会を逃すことになります。
- 神社・お寺で御朱印帳を分けるのがマナー
- 忘れた場合は「書置き御朱印」や「新しい御朱印帳の購入」も選択肢
- 記録として残るので参拝の思い出が深まる
関連記事:御朱印についての記事はこちら
お守り・おみくじ(返納用)
役目を終えたお守りやおみくじは、神社に返納するのが基本です。
- お守り・お札:おおむね1年を目安に返納
- おみくじ:吉兆に関わらず、気持ちが落ち着いたら返すのがおすすめ
- 納札所がない小さな神社では、大きな神社にまとめて返納してもOK
💡ポイント
紙袋などにまとめて保管しておくと、参拝時に一度に持って行けて便利です。
神社参拝を快適にする便利アイテム

必須ではありませんが、あると格段に参拝が快適になる持ち物があります。
季節や参拝スタイルに合わせて準備すると安心です。
虫除けスプレー・虫刺され薬(夏場の必需品)
神社は自然に囲まれた場所が多く、夏場は蚊や虫に悩まされることも。
特に山間の神社や緑豊かな境内では、虫除け対策は欠かせません。
- 虫除けスプレー:服や肌に吹きかけて予防
- かゆみ止め薬:ムヒやウナコーワなどを持っておくと安心
💡 夏の御朱印巡りや自然の多い場所での参拝では必携です。
関連記事:夏の参拝の虫除けについてはこちら
ウェットティッシュ(手水舎が使えない時)
小さな神社や無人の社では、手水舎の水が止まっていたり、衛生的に気になる場合もあります。
そんな時に役立つのがウェットティッシュ。
- 手や口を清める代わりに使用
- 御朱印帳やスマホが汚れたときの簡易クリーニングにも便利
紙袋やポーチ(お守りや御朱印をまとめる)
複数の神社を巡る場合、いただいた御朱印帳やお守りを整理する袋があると便利です。
- お守りをまとめる → 紛失防止
- 御朱印帳や書置き御朱印を入れる → 折れや汚れを防げる
💡 和柄のポーチや御朱印帳カバーを用意すると気分も上がります。
季節別の持ち物
参拝は一年を通して行うもの。季節ごとにあると助かるアイテムも紹介しておきます。
- 冬:手袋・カイロ(長時間並ぶ初詣に便利)
- 雨天:折り畳み傘やレインコート(境内は傘を差しづらい場合もあるのでレインポンチョがおすすめ)
- 夏:日傘・扇子・冷感シートなど熱中症対策グッズ
神社参拝の持ち物チェックリスト
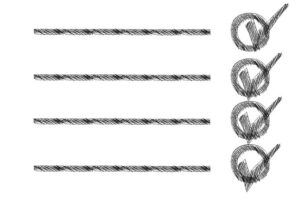
参拝の前に、以下の持ち物を確認しましょう。
プリントアウトやスクリーンショットで保存しておくと便利です。
✅小銭(お賽銭・おみくじ用に100円玉を数枚)
✅ ハンカチ・ミニタオル(手水舎や霊水に備えて)
✅ 御朱印帳(御朱印を集めている方は必携)
✅ お守り・おみくじ(役目を終えたものを返納用に)
\プラスすると安心!便利アイテム/
✅ 虫除けスプレー・かゆみ止め薬(夏場の参拝に)
✅ ウェットティッシュ(小さな神社や衛生面が気になる時)
✅ 紙袋やポーチ(お守りや御朱印をまとめる)
✅ 季節アイテム(冬の防寒具、雨天の折り畳み傘、夏の日傘など)
初詣におすすめの持ち物

初詣は一年の始まりに神様へご挨拶する特別な参拝。
普段の参拝と違い、寒さ・人混み・待ち時間といった状況があるため、少し工夫した持ち物が役立ちます。
共通してあると良いもの
- 小銭(多めに)
参拝者が増えるので両替は難しいです。100円玉を中心に準備しておきましょう。 - 返納用のお守りやお札
一年分をまとめて返す人が多いので忘れずに。 - 紙袋やポーチ
新しいお守りやお札をいただく機会が増えるので、まとめて収納できる袋が便利です。
大規模神社・混雑する場合
- 厚め防寒具(カイロ・手袋・マフラー)
真冬の夜間や早朝は特に冷え込みが厳しいため、しっかり防寒を。 - 暖かい飲み物(魔法瓶入りのお茶など)
長時間並ぶと体が冷えるので、体の内側から温まる飲み物が心強いです。 - 飴やチョコなどの軽食
行列中に小腹を満たす程度のもの。体力を保つのに役立ちます。
小さな神社・混雑が少ない場合
- 軽めの防寒具
昼間に参拝するならコートと手袋程度で十分。 - カメラやスマホ
家族写真や御朱印を残したい方は準備しておきましょう。
💡 初詣は「大規模参拝」と「地元参拝」で必要な物が変わります。
どちらに行くかを想定して、忘れ物がないように準備しておきましょう。
筆者おすすめ!神社参拝アイテム4選
参拝の必需品や便利グッズはいろいろありますが、その中でも「これは持っていてよかった」と強く感じるアイテムを4つご紹介します。
ミニタオル(必須度 ★★★)
手水舎で手や口を拭くだけでなく、霊水や水みくじに触れる際にも活躍。
神社参拝では思いのほか水に触れる場面が多いので、1枚あると安心です。
▶私はアフタヌーンティーリビングのミニタオルが大好き。しっかりしてるしかわいいのでおすすめです。
御朱印帳(必須度 ★★☆)
参拝の証を残せる御朱印帳。忘れると後悔することが多く、旅行や遠征時には特に必須。
デザインも豊富なので「お気に入り」を持つと参拝のモチベーションが高まります。
▶御朱印を頂くと参拝した実感が強く残ります。一生ものなのでぜひお気に入りのものを。
コインケース(必須度 ★★☆)
お賽銭・おみくじ・お守り購入など、現金を使う機会が多い神社では小銭の出し入れがスムーズ。
特に100円玉をきれいに収納できるケースは便利でおすすめです。
▶金運アップ効果もあるがま口財布。和柄のがま口財布はお賽銭用にぴったり。
虫除けスプレー(必須度 ★★☆)
夏場や緑が多い神社では必携アイテム。
参拝中に蚊に刺されて集中できなくなるのを防ぎます。小型スプレーをバッグに入れておくと安心です。
▶安心の日本製ならディート10%高配合のサラテクトがイチオシ。
💡 「持ち物リスト」と合わせて、これらのアイテムを準備しておけば大抵の参拝は快適に過ごせます。
この4つは私自身が“参拝の相棒”にしているアイテムです。
基本の持ち物リストと組み合わせて準備すれば、どんな神社参拝でも安心して臨めます。
まとめ|持ち物を整えて、心地よい参拝を

神社参拝は、ただの習慣ではなく「心を整える大切な時間」です。
持ち物をきちんと準備しておくことで、参拝がスムーズになり、神様への敬意も自然と形になります。
- 必須の持ち物:小銭・ハンカチ・御朱印帳・返納用のお守りやおみくじ
- 便利な持ち物:虫除けスプレー・ウェットティッシュ・紙袋やポーチ・季節の対策グッズ
参拝の度に「あ、忘れた!」と慌てることがなくなれば、より心静かに神様と向き合えるはずです。
ぜひ本記事のチェックリストを活用して、安心して参拝に向かってください。
準備を整えること自体が、すでにご利益へとつながる一歩になるでしょう。
都道府県別の神社仏閣まとめ 御朱印/御神塩/御神水(お水取り)/御神土(お土取り)
▶吉方へ旅行し神社仏閣を参拝して人生を好転させましょう