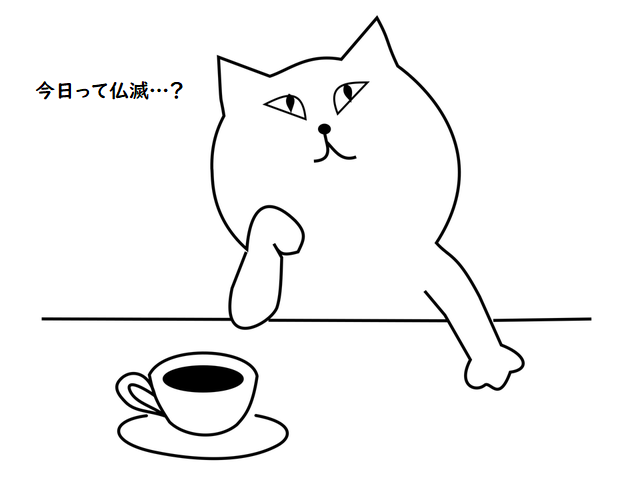
目次
六曜(ろくよう)とは、「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の6つの日を巡らせ、吉凶を占う暦注のひとつです。
日本では結婚式や葬儀、契約日などで意識されることが多く、「仏滅は凶、大安は吉」といった形で有名です。
しかし実際には、六曜に科学的根拠はなく、仏教とも関係がありません。
この記事では、六曜の意味や歴史、本当の由来を整理しつつ、「なぜ今も気にする人が多いのか」「どう向き合えばいいのか」を占い好きの視点から解説します。
六曜とは?

六曜(ろくよう)とは、暦(こよみ)に記される吉凶の目安で、「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の6種類から成ります。
結婚式や葬儀、引っ越し、契約などの場面で「今日は大安だから良い日」「仏滅だから避けたい」といった判断基準として使われてきました。
本来は旧暦をもとにした日取りの区分であり、現代の新暦に当てはめて使っているため、不規則に巡ることもあります。
また「大安=必ず吉」「仏滅=必ず凶」といった単純な決めつけではなく、それぞれに細かい特徴があります。
六曜の種類と意味(一覧表)
以下の表は、六曜それぞれの読み方・意味・特徴を一覧にしたものです。
六曜早見表
| 六曜 | 読み方 | 意味・吉凶 | よく言われる特徴 |
|---|---|---|---|
| 先勝 | せんしょう/せんかち | 午前は吉、午後は凶 | 早く行動すると良い |
| 友引 | ともびき | 朝夕は吉、正午は凶 | 葬儀を避ける日とされる |
| 先負 | せんぷ/せんまけ | 午前は凶、午後は吉 | 静かに過ごすのが良い |
| 仏滅 | ぶつめつ | 終日凶日 | 何事も慎むべきとされる |
| 大安 | たいあん | 終日吉日 | 結婚・契約・移転などに良い |
| 赤口 | しゃっこう/しゃっく | 正午のみ吉、それ以外は凶 | 火や刃物に注意する日 |
このように六曜は「吉日」「凶日」と単純に区切られがちですが、実際には時間帯ごとの違いもあります。
そのため「午前は良いが午後は凶」といった細かい区分も存在しているのです。
六曜は占いのように見えますが、実際には機械的なサイクルで巡る仕組みです。
「先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口」の順番で繰り返され、旧暦をもとにしているため、新暦では日付が飛ぶこともあります。
六曜の吉凶を一覧で見ていただくとわかる通り、実は“吉”とされる時間は意外に少ないのです。
6日に1回は万事凶とされる仏滅が巡り、さらに半日のみ凶とされる日も多くあります。
大手を振って丸1日活動できるのは「大安」くらい、と考えると、六曜は吉日より凶日のほうが多い暦注といえます。
六曜の起源と歴史

六曜の起源は中国にあります。
もともとは陰陽道や暦法の一部で、時間の区切りや吉凶を示すものとして使われていました。
日本に伝わったのは14世紀頃(鎌倉時代)とされ、その後、江戸時代に庶民の間で急速に広まりました。
江戸時代は町民文化が大きく花開き、識字率も向上したことで、暦や暦注が広く読まれるようになった時代です。
言葉遊びやゲン担ぎが好まれたこともあり、「今日は大安だから縁起がいい」「仏滅は避けるべきだ」といった六曜の考え方が定着しました。
本来の六曜は仏教や神道とは関係がありません。
たとえば「仏滅」という字面は仏教を連想させますが、実際には仏教由来ではなく、後から当てられた字です。
また「友引」ももともとは「友曳」と書かれており、「友を道連れにする」という語感から、葬儀を避けるべき日とされました。
こうした名称や意味づけの変化は、日本独自の言霊信仰や縁起文化と結びついた結果といえるでしょう。
六曜の本当の意味と誤解

六曜は「仏滅」「大安」といった強いイメージの字面から、宗教や深い信仰と結びつけられがちです。
しかし実際には、仏教や神道とは直接関係がありません。
仏滅について
「仏が滅する」と書くため不吉な印象を与えますが、仏教とは無関係です。
もともとは「空亡(くうぼう)」という名称で、「何もない」「空しい日」を表していました。
それが後に「仏滅」と書き換えられたことで、迷信的な意味が強まったのです。
友引について
現在は「葬式を避けるべき日」とされていますが、これも仏教由来ではありません。
語源は「友曳(ともびき)」で、「友を道連れにする」というイメージからそう考えられるようになりました。
実際には友引の日に葬儀が行われることもあります。
大安について
「大いに安し」と書くことから、すべてに良い日とされます。しかし、科学的・統計的な根拠はなく、あくまで文化的な“縁起担ぎ”としての意味合いにすぎません。
このように、六曜は古来の宗教教義ではなく、日本の言霊文化やゲン担ぎが色濃く反映されたものです。
つまり「信じる・信じない」は個人のスタンス次第といえるでしょう。
六曜は当たるのか?心理学から見る自己成就予言

六曜は「大安だからうまくいく」「仏滅だから失敗する」といった吉凶の目安として信じられてきました。
しかし、実際に六曜そのものが未来を決める科学的な根拠はありません。
ただし、人の心理には「占いが当たった」と感じさせる仕組みがあります。
自己成就予言(じこせいじゅよげん)
「今日は大安だから大丈夫」と思って行動すれば、自然と前向きな姿勢になり、物事がうまく進みやすくなります。
逆に「仏滅だからきっと悪いことが起こる」と思えば、不安や消極的な気持ちが行動に影響し、結果的に失敗しやすくなるのです。
つまり「占い通りの結果になった」と感じやすくなる心理作用が働きます。
血液型占いと同じ原理
「A型は几帳面」と言われれば、自分の行動の中から几帳面な部分を無意識に探して当てはめてしまう。
六曜もこれと同じで、自分の認識や行動次第で「当たった」と思えるようになるわけです。
このように、六曜を完全に否定するのではなく、心理的な作用を理解して上手に使うことで、ポジティブな効果を引き出すことが可能です。
現代での六曜の使われ方(結婚式・葬儀・契約・日常生活)

六曜は科学的な根拠はないものの、日本では今もなお生活のさまざまな場面で用いられています。特に「人生の節目」に関わる行事では、六曜を意識する人が少なくありません。
結婚式
結婚式は「大安」が圧倒的に人気です。
そのため大安は式場の予約が早く埋まり、料金も高くなることが多いです。
逆に「仏滅」は敬遠されがちですが、費用が安くなるため、六曜を気にしないカップルには狙い目とされています。
葬儀
「友引」は「友を道連れにする」と考えられたため、葬儀を避ける日とされてきました。
現代でも一部の斎場は友引を休業日にしています。
ただし宗教的には問題がないため、地域や家族の考え方によっては普通に葬儀を行う場合もあります。
契約・引っ越し・開店
新しいスタートを切る場面では「大安」を選ぶ人が多いです。
不動産契約や会社設立、店舗のオープン日などに大安を意識して日取りを決めるケースが見られます。
日常生活
カレンダーや手帳に六曜が記されていることも多く、「今日は仏滅だから用事は控えよう」と考える人もいます。
ただし若い世代を中心に「六曜を全く気にしない」という人も増えており、世代間での価値観の差が出やすい部分です。
念のため六曜を日常的に確認したい方は、六曜入りの手帳を使ってみるのもおすすめです。
引っ越しや旅行の日付は、六曜よりも日々変わる吉方位で調べるのがおすすめです。
💡関連記事:旅行風水(方位取り)のやりかたはこちら
筆者の考え:気にしないけど「大安」だけは活用する理由

私自身は、基本的に六曜を気にして生活してはいません。
日常の行動やスケジュールを「仏滅だからやめておこう」と制限してしまうのは、本来のチャンスを逃すことに繋がるからです。
しかし、その一方で「大安」だけは意識するようにしています。
理由はシンプルで、自分の気持ちを前向きに切り替える合図になるからです。
例えば、
- 新しい企画を始める日
- 遠方への旅行に出発する日
- 人に会う予定を入れる日
こうしたタイミングを「大安」に合わせると、「今日は縁起がいいから大丈夫」と自然に思えて、気持ちが前向きになります。
これは六曜の効力というより、心理的な安心感を利用しているにすぎません。
逆に「仏滅だから不運になる」という考え方は持っていません。
もし仏滅に大切な用事が重なっても、「自分に必要な流れだから来ている」と受け止め、むしろ積極的に取り組むようにしています。
つまり六曜は「縛られるもの」ではなく、「前向きな気分に切り替えるきっかけ」としてだけ利用するのが、ちょうどいい使い方だと考えています。
まとめ:六曜をどう取り入れるべきか

六曜は、結婚式や葬儀、契約などの大事な場面で今も意識される一方で、科学的な根拠はなく、宗教とも無関係な暦注です。
もともとは中国から伝わり、江戸時代に庶民文化の中で広まった“縁起担ぎ”にすぎません。
しかし、人の心理は「今日は大安だから安心」「仏滅だから不安」といった影響を受けやすく、結果として自己成就予言のように現実の行動や結果に作用することがあります。
そのため六曜を「信じる・信じない」の二択で考えるよりも、自分にとって都合よく活用するのが賢い向き合い方です。
たとえば、
- 「大安」を新しいことを始めるきっかけにする
- 「仏滅」でも必要な用事なら気にせず進める
- 周囲が気にしている場面(結婚式や葬儀など)では配慮する
といった柔軟な取り入れ方ができます。
六曜は本来、私たちを縛るためのものではなく、気持ちを整えたり行事を彩ったりする“文化的な目印”と考えると良いでしょう。
迷信に振り回されるのではなく、自分の人生にプラスになる形で利用していくことをおすすめします。













