
目次
神社で授かる「清め塩(御神塩)」は、古くから 厄除け・浄化のための特別な塩 として大切にされてきました。
玄関に盛って邪気を防ぐ、神棚に供えて空間を清める、携帯してお守り代わりにするなど、日常生活の中で幅広く活用できます。
ただ、「神社でもらった塩はどう使うの?」「余ったら食べてもいいの?」「処分はどうするの?」といった疑問を持つ方も多いはず。
この記事では、
- 清め塩の意味と効果
- 基本・応用の使い方
- 保存と処分の方法
をわかりやすく解説します。
さらに、便利な盛り塩グッズや携帯アイテムもご紹介しますので、神社で見かけたときに迷わず取り入れられるよう、参考にしていただければ嬉しいです。
清め塩とは?神社でもらえる塩の意味と効果

「清め塩(御神塩)」とは、神社によって呼び方は異なりますが、いずれも 神様の御前に供えられたあとに下げられる特別なお塩 です。
塩そのものにも海の恵みに由来する浄化作用がありますが、神前に供えられた塩には 神様の霊力が宿る とされ、特に以下のような効果があると伝えられています。
- 厄除け … 不運や災いを遠ざける
- 邪気払い … 人や空間にたまった悪い気を浄化する
- 結界の力 … 家や店舗を守り、良い気を呼び込む
神社で授与される清め塩は、スーパーで買える精製塩とは違い、神様の「気」が入っているので強力です。
また、塩と似た授与品に「御神土」「清め砂」などがあります。
これらも浄化や結界のために用いられますが、用途や由来が少しずつ異なります。清め塩とあわせて覚えておくと便利です(※違いについては後半で解説します)。
清め塩の基本的な使い方

清め塩は、特別な儀式をしなくても日常の中で取り入れやすい浄化アイテムです。
まずは代表的な2つの使い方をご紹介します。
神棚へのお供えに使う
神棚には本来、伊勢神宮に倣って「米・塩・水」を清浄な器に供えるのが基本とされています。
塩を供える場合も同様に、白い陶器の小皿や塩皿に少量を盛るのが一般的です。
厳密な分量や盛り方の決まりはありませんが、ひとつまみ程度を小さな山のように盛り、心を込めてお供えするとよいでしょう。
お供えを新しくするタイミングは本来は毎日が理想ですが、現代の生活では難しいため、毎月1日と15日 に取り替えるご家庭も多いです。無理のない範囲で続けられるリズムを作ることが大切です。
玄関や店先に盛り塩を置く
玄関は「人と運気の出入り口」とされ、神棚と同じように清らかに保つことが大切です。
そこに塩を盛る習慣は、古くから 邪気の侵入を防ぎ、結界を張る方法 として伝えられてきました。
盛り塩を行う際は、白い小皿や陶器の器に塩を少量盛り、玄関や店舗の出入口に置きます。
形や量に厳格な決まりはなく、三角錐・円錐型など整えやすい形に盛れば十分です。
一般的には、
- 自宅では玄関の内側または外側に一皿
- 店舗では入口の左右に一皿ずつ
といった形で置かれることが多いです。
交換の頻度は毎日が理想ですが、無理のない範囲で定期的に取り替えることが大切です。
特に神棚と同じく、毎月1日と15日 を目安に新しくすると、生活のリズムに馴染みやすいでしょう。
盛り塩は単なる風習ではなく、「清浄な場を保つ心がけ」として現代でも実践しやすい開運法です。
清め塩の応用的な使い方

基本のお供えや盛り塩に加えて、清め塩は日常のさまざまな場面で取り入れることができます。
ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。
携帯してお守りにする(方災除け)
外出や旅行の際、方角が気になる時に小さな塩を和紙や懐紙に包み、財布やポーチに入れて持ち歩くと「身を守る護り」となります。
包み方に決まりはありませんが、薬包みのようにこぼれにくい形にすると扱いやすいです。
現地の伝承でも、沖縄の「ぬちマース(命の塩)」など、塩をお守りとして携帯する習慣があります。
「なんとなく不安な日」や「気が重い予定がある日」にも取り入れやすい方法です。
室内に置いて空間を清める
塩は「気を吸う」とされ、部屋の四隅や空気の重い場所に少量盛ると場が落ち着くと伝えられています。
- 白い皿に小山のように盛る
- 置くのは四隅や気になるスペース
- 3時間ほどで回収して処分する
長時間放置すると吸った気が逆に滞るとも言われるため、使い終わった塩は水に流して処分するのが安心です。
掃除や換気とあわせると効果的で、空間の雰囲気がすっきり整います。
入浴に使う(厄落とし風呂)
湯船に塩を大さじ2杯ほど入れて入浴すると、心身を浄化しリフレッシュする「厄落とし風呂」となります。
精製されていない粗塩でも代わりに使えますが、神社でいただいた清め塩を使うと厄を落とす効果が強力です。
- 疲れや気分が重い日
- 人混みや職場で消耗した日
- 凶方位に出かけた後
こんな時におすすめです。
入浴後は必ずお湯を流して「厄を水に流す」意識を持ちましょう。
💡関連記事:別の邪気払いの方法についてはこちら
清め塩の保存方法と注意点

神社でいただいた清め塩は、御守りと同じく大切に扱うのが基本です。普段の台所用の塩とは分けて保管しましょう。
清め塩の保存方法
- 湿気を避け、清浄な場所に置く
- 小袋や和紙に包み、引き出しや神棚の近くに保管する
- 長期保存するより、適度に使って新しくいただくのが理想
清め塩は食べてもいいの?
神社によっては「清め塩は食用ではありません」と案内される場合もあります。
ただし「御神前に供えた塩を食べて体内を清める」とする風習もあり、地域差があります。
迷ったときは いただいた神社の説明や授与所での案内 に従うのが安心です。
清め塩保管の注意点
- 時間が経つと湿気を吸いやすいため、固まってきたら使い切りを意識する
- 普通の調味料と混ざらないよう、容器や袋を分けて保管する
清め塩は「持っていること」自体が護りになると考えられているため、無理に長期保存するより、使い切って新しいものをいただく方が気持ちよく扱えます。
清め塩の処分方法

清め塩は、使い終わったらそのまま放置せず、感謝を込めて処分するのが大切です。
水に流す
もっとも一般的なのは、使い終わった塩を 台所や洗面所の水と一緒に流す方法です。
「水に流す」という言葉の通り、塩が吸った邪気も一緒に清められると考えられています。
ゴミとして処分する場合
どうしても難しいときは、新聞紙や半紙など清浄な紙に包み、感謝を伝えながら処分する方法もあります。
ただし、気持ちの上では「水に流す」ほうが安心感を持てるでしょう。
清め塩と御神土・清め砂との違い
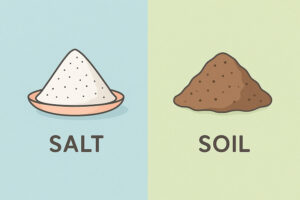
神社では「清め塩」のほかに、よく似た授与品として「御神土(おしんど)」「清め砂」を見かけることがあります。どれも浄化や結界に用いられますが、それぞれ役割が少しずつ異なります。
清め塩(御神塩)
- 神前に供えられた塩を下げたもの
- 厄除け・邪気払い・結界として使う
- 神棚や玄関への盛り塩、入浴など幅広い用途に使える
御神土・清め砂
- 神社の境内や聖域の「土」「砂」をいただいたもの
- 家の敷地や建物の四隅に撒いて結界を張る
- 引っ越し・新築・地鎮祭など土地に関わるときに使われることが多い
いずれも「神様の力が宿った自然の恵み」であり、塩・土・砂という違いはありますが、共通して空間や人を清める役割 を持っています。
👉 詳しくは関連記事「御神土・清め砂の使い方」にもまとめていますので、あわせてご覧ください。
💡関連記事:御神土・清め砂についての記事はこちら
清め塩に関するよくある質問(Q&A)

Q. 清め塩は車や鞄に入れても効果はありますか?
A. はい。
鞄や車は「移動する空間」として邪気を受けやすいとされます。
小袋に入れた塩を常備しておくことで、交通安全や日々の移動を清らかに守ると考えられています。
Q. 湿気で固まった清め塩はどうすればいい?
A. 使い切りを意識して処分しましょう。
無理に崩して使い続けず、感謝を込めて水に流し、新しい塩に取り替えるのがおすすめです。
お風呂の浄化に使ってしまうのもひとつです。
Q. 盛り塩を置く場所は、玄関以外でもいいの?
A. はい。
寝室の四隅や、なんとなく空気が重いと感じる部屋の隅にも置けます。
3時間ほどで回収するのを目安にすると安心です。
Q. 神社でいただいた清め塩と、市販の粗塩はどう違うの?
A. 大きな違いは「神前に供えられたかどうか」です。
市販の塩も浄化には使えますが、神社の清め塩は「神様の前に供えられたあと授与されたもの」で、信仰的な意味合いが強いとされています。
おすすめの清め塩アイテム
盛り塩セット(型+皿)
盛り塩をきれいに整えるには、専用の型と皿があると便利です。初心者でも美しい三角錐や円錐型が作れるので、浄化の効果を意識しやすくなります。
▶きれいな八角錐の盛り塩を作ることができる定番アイテムです。
携帯用の和紙袋(匂い袋・文香用)
神社でいただいた清め塩を持ち歩くときは、和紙や懐紙に包むのが基本ですが、匂い袋・文香用の小さな和紙袋 を使うとさらに便利です。
袋に入れるだけで塩がこぼれず、手軽に安心して携帯できます。
▶こちらはアイロンで閉じることができ、簡単に清め塩を使った携帯用のオリジナル守り塩が作れます。
盛り塩専用の小皿・ガラス器
神棚にお供えする場合は、伝統に倣って 白い陶器の小皿 を使うのが一般的です。
一方で、玄関やリビングに盛り塩を置く際には、透明感のあるガラスの器 もおすすめです。
光を受けて美しく見え、インテリアにも馴染みます。
盛り塩用の器は普段の食器とは分けて、専用のものを用意すると清浄さを保ちやすいでしょう。
▶盛り塩に使う器はシンプルで4枚以上のセット物がおすすめ。意外と割れたりするので、予備も含めて6枚セットだと安心。
まとめ|清め塩は日常で使える開運アイテム

神社で授与される「清め塩(御神塩)」は、特別な力が込められた浄化アイテムです。
厄除けや邪気払いのために、日常でも気軽に取り入れることができます。
主な使い方をおさらいすると:
- 神棚に供えて空間を清める
- 玄関や店舗の入口に盛り塩を置く
- 携帯してお守りにする
- 部屋の四隅や気になる場所を浄化する
- 入浴に入れて心身を整える
処分するときは「水に流す」のが基本。
保存も長期にこだわらず、定期的に使い切って新しいものを授かると清浄さを保てます。
また、日常で使いやすくするために 盛り塩セット・和紙袋・ガラス器 などのアイテムを取り入れるのもおすすめです。
清め塩は難しい作法を必要とせず、ほんの少し意識して取り入れるだけで、空間や気持ちを整えてくれる存在です。
神社で見かけたときは、ぜひ一度授かって日常に活かしてみてください。
※御神塩を扱ってる神社はこちらもご参考に
都道府県別の神社仏閣まとめ<御朱印><御神塩><御神水(お水取り)><御神土(お土取り)>
















