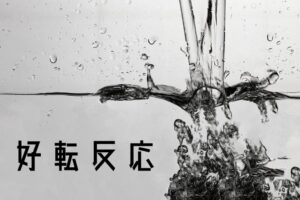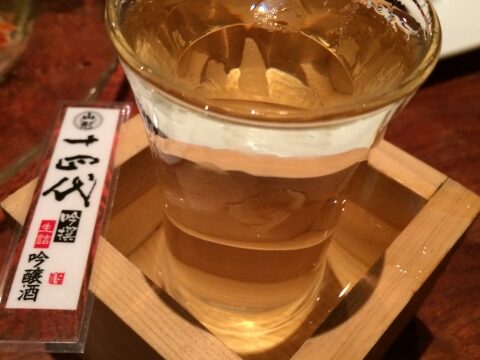目次
神社でご祈祷や参拝をしたときにいただく「御神酒(お神酒)」。
せっかく授与されたものの、「これっていつ飲めばいいの?」「飲めない場合はどうすれば?」 と迷った経験はありませんか?
御神酒は、神様にお供えされた特別なお酒です。
いただき方ひとつで、感謝の気持ちを深めたり、開運の行動につなげたりすることができます。
この記事では、
- 御神酒の意味と由来
- 飲むタイミングや保存方法
- 飲めない場合の活用法(料理・お清め・酒風呂)
- 厄払いなどスピリチュアルな意味
- よくある疑問Q&A
をまとめて解説します。
「神社で御神酒を頂いたけど、どうすればいいのか」を迷ったときの答えとして、ぜひ参考にしてください。
寒川神社で八方除けの御祈祷をして頂きました!御祈祷とお土産レポート♪
御神酒とは?意味と特徴
御神酒の基本的な意味

「御神酒(おみき)」とは、神社で神様にお供えした後に下げたお酒のことを指します。
一般にスーパーなどでも「お神酒」と表記された瓶が売られていますが、これはあくまで神前用に用意された日本酒で、実際に神社で奉納された御神酒とは区別されます。
神社でいただく御神酒は、神様に一度お供えされたことで「神気が宿る」と考えられる特別なお酒です。
たとえば、神奈川県の寒川神社では、地元の酒蔵である熊澤酒造が醸す日本酒が御神酒として授与されています。
実際、寒川神社の御神酒は味わいもよく、美味しいと評判です。
神気とともに土地の恵みを口にできるのも御神酒ならではの魅力といえるでしょう。
神人共食と直会(なおらい)

御神酒をいただく行為は、古代から「神人共食(しんじんきょうしょく)」と呼ばれてきました。
これは、神様にお供えしたものを人も口にすることで、神と人が同じ食卓を囲むという考え方です。
神事の後に供物を分け合うことを「直会(なおらい)」といい、参列者が御神酒や供物をいただくことで、神様の霊力が宿った食べ物を体に取り込み、ご加護を分かち合うとされてきました。
この考え方は、現代の神前結婚式にも受け継がれています。
神前結婚式では、新郎新婦が御神酒を交わす「三々九度」の後、両家の親族が御神酒をいただく「親族固めの盃」という儀式があります。
これもまた、神人共食の考え方が受け継がれたもので、御神酒を通じて神様と人、そして両家の絆を結び固める行為といえます。
神人共食は、単にお酒や食物を味わう行為ではなく、
- 神様と人との距離を縮める
- 神の力を受け取る
- 共同体としてのつながりを深める
といった意味合いを持ちます。
このように、御神酒は「神様との絆を確認する特別なお酒」として、古来より大切にされてきたのです。
神様とお酒の関係

日本には古くから「御神酒あがらぬ神はなし」という言葉があり、これはお酒を捧げられない神様はいないという意味です。
それほどまでに、お酒は神様にとって最も身近で大切な供物とされてきました。
お酒は米と水から造られる「自然の恵みの結晶」であり、人の労力と祈りが込められた神聖な飲み物です。
調理の手間がなく、その場ですぐに捧げられる点も、神事に適していました。
また、お酒は神気を宿しやすいと考えられている側面もあります。
そのため、神様にお供えした御神酒は、神の力を分けてもらう媒介として特別視されてきたのです。
ただし、御神酒の神気は時間とともに薄れていくとされます。
授与された御神酒は長期間置いておくのではなく、なるべく早めにいただくことが推奨されます。
御神酒はいつ飲む?

飲むタイミングと賞味期限
御神酒をいただくタイミングには、厳密な決まりはありません。
神様にお供えされた特別なお酒であることから、なるべく早めにいただくのが良いとされています。
特に瓶に入った御神酒は、一般の日本酒と同じく、時間とともに風味が落ちていきます。
保存は直射日光を避けて冷暗所に置き、開封後は数日〜1週間以内を目安にいただくのがおすすめです。
神気は時間の経過とともに薄れていくと考えられているため、授与から日を置かずに口にする方が「ご加護を受けやすい」と考えられます。
少しずつ飲む vs 一気に飲む
早い方が神気が強いとはいえ、御神酒は必ずしも一度に飲み切る必要はありません。
食卓で少しずつ味わう、就寝前に一口いただくなど、感謝を込めてゆっくりと味わうことが大切です。
一気に飲むよりも、毎日少しずつ取り入れることで「神気が体に定着する」という説もあります。
体質や体調に合わせて、無理なく楽しむのが理想です。
開運行動「お水取り」との関連
開運法のひとつに「お水取り」があります。
これは吉方位で汲んだ水を少しずつ飲むことで、運気を体に取り込む方法です。
御神酒をいただく際にも、この「お水取り」と同じ考え方を応用することができます。
一度に飲み干すのではなく、感謝を込めて少しずついただくことで、神気を自分の身体に馴染ませる効果があります。
💡関連記事:開運『お水取り』のやり方と効果について
飲めない・飲まない場合の御神酒の使い方
御神酒は本来「いただく」ことが基本ですが、未成年や妊娠中・授乳中の方、またお酒が苦手な方などは飲むことができません。
そんなときも、御神酒を無駄にせず、感謝とともに神気を受け取る方法があります。
料理に活用する(料理酒として)

御神酒は良質な清酒であることが多く、料理に使うことで風味を引き立ててくれます。
加熱すればアルコール分は飛ぶので、未成年や妊婦の方でも安心です。
煮物や焼き魚の下味、肉の臭み消しなど、日常の料理に少しずつ取り入れると良いでしょう。
神様から授かったお酒を日々の食卓に活かすことで、家族全員で御神酒のご加護を分け合うことができます。
専門家の見解も紹介します。
【産婦人科医監修】妊娠中に料理酒は使っても大丈夫?影響について(外部リンク)
家のお清めに使う(撒く・拭き掃除)

御神酒をそのまま玄関先や家の四隅に少量撒くことで、場を清める方法もあります。
匂いが気になる場合は水で薄め、スプレーにして清掃や拭き掃除に使うのもおすすめです。
また、夏の風習である打ち水にも清めの効果があるとされてきました。
水に少量の御神酒を混ぜて玄関先や庭に撒けば、涼を呼ぶと同時に場を祓い清める意味も持たせることができます。
アルコールに敏感な方は注意が必要ですが、場を清める気持ちで用いることで、邪気祓いの意味合いが強まります。
💡関連記事:掃除と断捨離で運気アップ
酒風呂で神気を浴びる

御神酒をお風呂に入れて「日本酒風呂」として使うのも、古くからの浄化法のひとつです。
全身で神気を浴びることができ、血行促進やリラックス効果も期待できます。
ただし、アルコールに弱い方や肌が敏感な方は注意が必要です。
心配な場合は料理に活用するのが安心です。
💡関連記事:邪気払いについて(日本酒風呂の記載あり)
御神酒のスピリチュアルな意味

御神酒と「き」の語源
古代日本語では、酒そのものを「き」と呼ぶことがありました。
この「き」は「気」と同源で、生命力・霊力・神気を意味します。
つまり「御神酒(おみき)」とは、「尊い・神聖な気(酒)」という意味合いを持つのです。
この考え方を裏づけるように、古代の神話や地名にも「き」が色濃く残っています。
たとえば、『古事記』『日本書紀』では酒を「き」と表す表現が登場し、生命力を満たす飲み物として描かれています。
また、宮崎県の都萬神社(つまじんじゃ)に伝わる「木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が三人の皇子を育てる際、母乳の不足を補うために甘酒を用いた」という伝承は、酒が命を養う力を持つと理解されていた象徴的なエピソードです。
さらに、地名や神社にも「き」は息づいています。
福井県の気比神宮(けひじんぐう)は、仲哀天皇を迎える際に神が酒を献じた故事(日本書紀)があり、酒と神気が結びついた古代信仰を今に伝えています。
また、京都府の貴船神社(きふねじんじゃ)は「水の気」を司る神を祀り、酒や水に宿る「き」の力を象徴しています。
こうした語源や伝承を踏まえると、御神酒をいただくことは、単なる日本酒を口にする以上の意味を持ちます。
神様の気=生命力を体に取り入れる行為として理解できるのです。
厄払いと御神酒
御神酒は、古来より「厄を祓い、新しい力を授かる」象徴とされてきました。
神社で厄除けや祈願のご祈祷を受けた際に授与される御神酒は、神様の霊力が宿った清らかな酒と考えられています。
いただくことで「厄を流し去り、新しい気を体に取り込む」意味があり、浄化と再生の両面を兼ね備えています。
そのため御神酒は単なる縁起物ではなく、厄払いの仕上げとしての役割を果たしているのです。
飲めない方の場合でも、料理に使ったり、清めに撒いたりすることで神気を取り込み、厄落としの意味を実感できます。
Q&A:御神酒に関するよくある疑問

御神酒は未成年でも飲める?
未成年が御神酒を飲むことは法律上できません。
ただし、神様のご加護は「飲む」という形だけでなく、料理に使ったり、お風呂に入れて浸かることでも受け取れると考えられます。
妊娠中・授乳中にいただいた御神酒はどうする?
妊娠中・授乳中はアルコールを避ける必要があります。
その場合は、料理に活用してアルコールを飛ばしていただくのがおすすめです。
また、ご家族が代わりにいただいて「母子の無事を願う」「家族全体の代表として厄を払う」という形も良いでしょう。
賞味期限や保存は?
御神酒は基本的に清酒なので、普通の日本酒と同じように扱えば大丈夫です。
賞味期限も記載されています。
直射日光を避け、冷暗所で保存しましょう。
開封後は酸化で風味が落ち、また持ち帰ってから少しずつ神気も薄れていきます。
数日〜1週間以内を目安に、早めにいただくのがおすすめです。
盃や容器はどう処分する?
御神酒が入っていた盃や瓶は、基本的には一般の食器や空き瓶と同じように処分して問題ありません。
気になる場合は、
- きれいに洗ってリサイクルに出す
- 神社に返納する
- 塩で清めてから処分する
といった方法をとると安心です。
記念にとっておくのも良いでしょう。
スーパーのお神酒との違いは?
スーパーなどで売られている「お神酒」と、神社でいただく「御神酒」は区別されます。
市販のお神酒は「神前に供えるための日本酒」であり、実際に神様にお供えされたものではありません。
一方、神社で授与される御神酒は「一度神前に捧げられた酒」であり、神気が宿る特別なものと考えられます。
御神酒をさらに開運につなげる方法は?
御神酒をいただく際は、普通の盃で十分ですが、お気に入りの酒器を使うことで「喜びの気」を受け取りやすくなります。
また、金箔を浮かべて飲むことで、神気とともに金気も体に取り込み、金運アップにもつながるとされます。
こうした特別な楽しみ方をすることで、御神酒をより豊かに味わえるでしょう。
さらに、季節や行事に合わせて工夫するのもおすすめです。
たとえば「月見酒」の風習を参考に、月を眺めながら御神酒をいただくのも開運アクションのひとつです。
💡関連記事: 月見酒のやり方はこちら
御神酒を楽しむときにおすすめのアイテム
・[びいどろ酒器セット(楽天市場)]
・[食用金箔(楽天市場)]
まとめ

神社で授与される御神酒(お神酒)は、神様に一度お供えされた特別なお酒です。
いただくことは、神様の「気=生命力」を体に取り入れる行為であり、古来から神人共食の伝統として大切にされてきました。
飲むタイミングに厳密な決まりはありませんが、
- なるべく早めにいただく
- 感謝の気持ちを持って味わう
ことが大切です。
もし飲めない場合でも、料理に使ったり、家のお清めや酒風呂に活用したりすることで、神様のご加護を日常に取り入れることができます。
形式や方法よりも大切なのは、敬意と感謝の心です。
その心があれば、御神酒を通して神様の恵みをいただき、日々の暮らしに安らぎと力を得ることができるでしょう。
ちなみに、酒造の神として崇敬を集める京都の松尾大社には「酒の効能(十徳)」が記されたお守りがあります。
そこには「お酒は百薬の長」との考えが示されており、古来より酒そのものが尊ばれてきました。
御神酒もまた、感謝を込めて美味しくいただくことで、神様のご加護を受け取れるのです。
都道府県別の神社仏閣まとめ 御朱印/御神塩/御神水(お水取り)/御神土(お土取り)